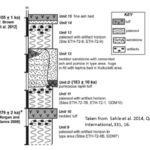エチオピアのキビッシュ層群の層序学と年代:stratigraphy and age of the Kibish formation Ethipia
エチオピアのキビッシュ層群の部層Iから出土したOmo IとOmo IIの人類化石は初期のホモ・サピエンスと考えられておりその年代は196kaと推定されている。部層Iのナカアキレタフの直接年代は196±2 kaであり、部層IIIにあるアリヨタフの年代は104±1 kaである。これらが上限と下限を与える。実際の化石年代は同じ部層の下にあるナカアキレタフに近い年代を持つと考えられてきた。両者の間にあるKHSタフの年代を推定することが、この化石の年代の下限を押し上げるために重要である。これまで、キビッシュ層…