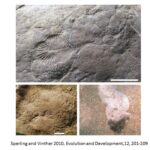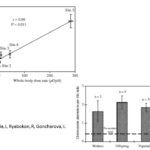デッキンソニアの平板動物との類似性と原生代における後生生物の食餌法:Dickinsonia and the evolution of late Proterozoic metazoan feeding modes
デッキンソニアとその這った後の化石(左)とその動物の系統樹上での推定分岐位置(右)ディッキンソニアは、エディアカラ生物群の中で最も目立つ生物であるが、系統学上の位置は、議論の的になってきた。Sperling and Vinter (2010)は、ディキンソニアが、現在の世界の熱帯の海に広くみられる平板生物(後生動物)と類似性が高いと結論した。現生の平板動物(センモウヒラムシ)はディッキンソニアと比べて、大きさと軸方向の構造に関して違いがあるが、これらの差は、基幹グループと分岐グループの差で説明できる…