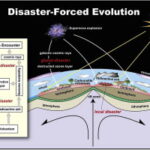ゲノム侵入としての雑種形成: Hybridization as an invasion of the genome
異なった種の間の雑種形成は、植物では普遍的だが、動物では不自然で異常であるとこれまで考えられてきた。そこで、自然環境における植物と動物の種間雑種形成を調べてみた。その結果、少なくとも植物種の25%、動物種の10%が雑種を含んでおり潜在的な他種からの遺伝子侵入の可能性を持っていることが明らかになった。そのほとんどが分化直後の若い種だった。自然環境の中で種は、その分化後数百万年の間は、隔離が完全でない場合がある。したがって、できたての種は、その分化開始から、最終的な繁殖隔離が成立するまでの長い間、同所的…
人工多能性幹細胞を誘導する遺伝子群と多細胞生物の進化:Genes induce pluripotent stem cells and the evolution of multicellular organisms
山中の発見は4つの遺伝子(Oct3/4、SoX2、c-Myc、Klf4)を細胞の中で同時に発現させると万能幹細胞になるというものだった(Takahashi and Yamanaka 2006)。Oct3/4とSox2は初期胚と幹細胞において、万能性の維持の機能を持っている。一方、c-MycとKlf4とは癌に関係する遺伝子である。c-Mycはヒストンのアセチル化を誘導する遺伝子らしい。Klf4はMycによって誘導されるアポトーシスを抑制する機能を持っていると言われている。さて、Sox2は、細胞分化に深…