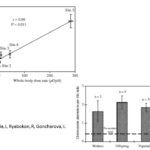黒海底におけるメタンガス漏出による石灰析出とそれに伴う微生物集団:Concretionary methane-seep carbonate and associated microbial communities in Black Sea sediments
メタン漏出地点にある析出石灰岩北東黒海のガス漏出地点は、嫌気的なメタンをエネルギー源とする生態系の研究に適している(Reitner et al. 2005)。メタン酸化に伴う石灰の析出がメタン漏出点の周りに堆積している。その一部は微生物マットで覆われている。この微生物の中に住む硫酸還元菌と古細菌がメタンの無酸素酸化を進めていると推定されている。微生物の代謝は、13Cがかなり欠乏した石灰の析出を支えている。硫酸還元菌は細胞内にグレイジャイト(Fe3F4)を包含物として持っており、鉄サイクルが微生物集団…