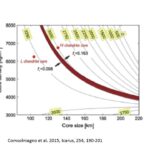硬骨魚類の海水適応ホルモンを探る:Exploring novel hormones essential for seawater adaptation in teleost fish
海生の魚類は高い浸透圧を持つ海水の中で脱水してしまうが、腸で吸収された過剰なイオン、特にNa+とCl-を排泄する能力を持っていれば、周りの海水を飲んでバランスを保つことができる。このような耐塩性機構には、ホルモンが重要な役割を果たしている。比較ゲノム学の研究から、硬骨魚類で、Na+を放出し、血管降圧性の性質を持つホルモンが多様に発達していることが分かってきた(Takei et al. 2008)。これらのホルモンは、硬骨魚類の海水での生存と水中における低い動脈圧の維持に重要である。海生のメクラウナギ…
コンドリュールの形成条件: The formation conditions of Chondrules
コンドリュールはだいたいミリメートルぐらいの大きさの主成分がケイ酸の球で、コンドライトと言われる原始的な隕石の主成分である。それらは、太陽系の中の内側部分の最も激しい現象の結果、溶融液滴として形成されたと考えられている。コンドリュールの形成条件やあまりよくわかっていない。Alexander et al. (2008)は、揮発性の元素であるナトリウムの濃度がコンドリュールの形成の間あまり変わっていないことを見出した。ナトリウムの蒸発を食い止めるためには、これまで考えたよりも桁違いに固体密度が高い領域で…
小惑星ベスタにおける物質分化: Material Differentiation in Asteroid Vesta 4
小惑星ベスタは、HED(hawardite, eucrite, and diogenite)玄武岩質エイコンドライト隕石の母天体と考えられている。これらの玄武岩質隕石は、Calcium-Alminium rich Inclusion (CAI)の析出(太陽系形成の開始時間として一般に使われている)から300万年以内に分化した母天体から形成されたと考えられている。この形成年代は、巨大惑星の形成と初期進化の時期と一致しており、その軌道の大規模な再構成と移動の時期にすでに母天体が存在していたことになる。探…