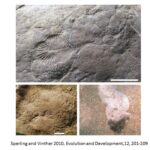人工多能性幹細胞を誘導する遺伝子群と多細胞生物の進化:Genes induce pluripotent stem cells and the evolution of multicellular organisms
山中の発見は4つの遺伝子(Oct3/4、SoX2、c-Myc、Klf4)を細胞の中で同時に発現させると万能幹細胞になるというものだった(Takahashi and Yamanaka 2006)。Oct3/4とSox2は初期胚と幹細胞において、万能性の維持の機能を持っている。一方、c-MycとKlf4とは癌に関係する遺伝子である。c-Mycはヒストンのアセチル化を誘導する遺伝子らしい。Klf4はMycによって誘導されるアポトーシスを抑制する機能を持っていると言われている。さて、Sox2は、細胞分化に深…